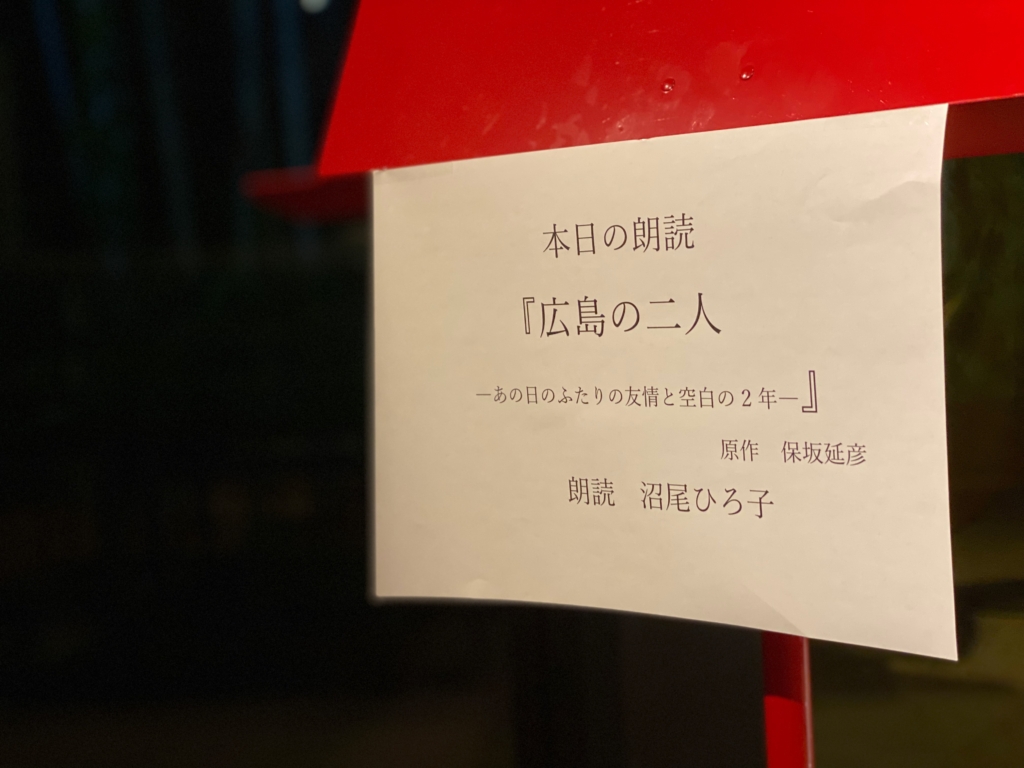
19時。静かに声がおりてきた。声は自然に発せられる。その瞬間に、私は私でなくなるのだ。
1945年8月6日。5歳のミツ子と母あつこの日常から物語ははじまる。次に、80歳のミツ子が、今まで生きながらえさせてくれた島谷隆三との出会いを語る。そして、ミツ子が翻訳をたくされた脚本「広島の二人」。
ミツ子の語りは静謐であたたかだ。脚本は、シーン、描写に飾り気がないから無機質。それでいてセリフは生の臨場感。ミツ子の中で父藤田純は別に人のようだ。なんともせつなく、泣けてくる。これほどまでに、愛にあふれた日常が、空白なのだ。なんて残酷なんだろう。これが戦争。
ミツ子と同じ広島出身の脚本家島谷隆三は、ただミツ子をしあわせにすることで、戦争のもたらしたものへの怒りとやりきれなさを、ちがったものに変えたかったのだ。自分がやるべきこと、自分ができることで。
二人。
ミツ子と島谷隆三
島谷隆三と安藤明夫
藤田純とアーサー・ダニエルズ
あつこと藤田純
ミツ子とあつこ
〜と〜
一人じゃない。
二人。
一人にしてはならない。
だから、ミツ子はしあわせに生きた。
今日、朗読したかった。今日じゃなきゃだめなのだ。
1時間をとうに超えて、ミツ子から私にもどってきた。
ふと我に返ると、顔はぐしゃぐしゃだった。
終わってから、みんな席をたとうとしない。なにか、口に出して言わなければと懸命に言葉を紡ぎ出して。気がつくと、2時間が過ぎていた。この「時」を愛おしんで。
やっぱり私がやるべきこと、私にできることは、声で伝えることなんだ。

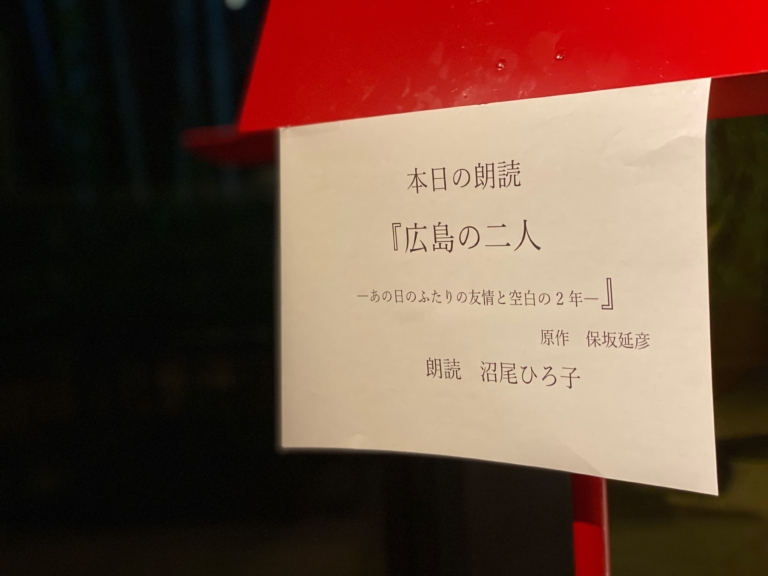








コメント